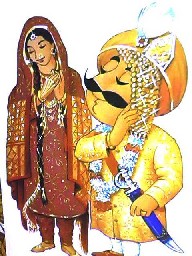
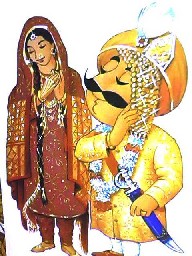
![]()
| 「皆様、当機は関西國際空港を定刻に離陸しました。 次の寄港地カルカッタまでの飛行距離は6000マイル、飛行所要時間は八時間です。途中お昼食とご夕食のサーヴィスをさせていただきます」 世界初の海上國際空港とし1994年に開港した大阪泉南の関西國際空港を、今離陸したエアー・インディア機のハイテク・ジャンボ機が、一機、軽快なジェット音をなびかせ機首を南に向けてぐんぐん高度を上げてゆく。 機の南旋廻につれ、群青の大阪湾に四月の陽光がキラキラ反射して、泉南の山並みが遥か下の方で斜めに後方へ流れ去る。 「只今、禁煙とシートベルト着用のサインが消えましたが、飛行中の揺れに備え、お座席のベルトは軽くお締めください」 エクゼクティブ・クラスのスーパー・シートの一隅に身を沈め、日本人スチューワーデスのアナウンスに耳を傾けながら、緊張の為か肩でフッとため息をついた若い女性客がいる。 人懐っこい細面の顔に笑うと白い歯がこぼれ、年のころ三十歳前後であろうか旅なれたキャリア・レディの雰囲気を漂わせているものの、よほど大事な資料がはいっているのだろう、膝にのせたアルマーニの細身のアタッシエケースを緊張気味にシッカリ抱えている。 さ〜て、あなたらな、この場面でこの女性客の旅行目的は何だと思いますか。 勿論観光旅行ではなさそう、間違いなくビジネス旅行でしょう。 でもどんなビジネスかな? お教えしましょうか。 そうです、一週間後に控えたカルカッタで行われる今年度の紅茶の新茶オークションに立ち会う為、この女性、今日、日本を旅立ったのです。 例年の事ながら、いつも新茶のこの時期になると、世界中のベテランの茶商人がカルカッタに集まり、ホットな商戦が繰り広げられるのです。 これからの稿で、「ティー・テイスターのお話」、 が然し、カルカッタのオークション(紅茶の競り売り)も又極めて興味深いテーマの一つです。 それになんと言っても、今、飛行で刻々とカルカッタに向かうあの美人ビジネス客が、世界の紅茶商人を相手にどんな買いつけをするのか、その活躍振りも見たいものです。 本当のところ、まだ紅茶のお話など何もしていないのに、もうここら辺でチョットカルカッタの「オークション物語」でもと寄り道したくなりましたが、「競り」のお話は機会があれば稿を改めるとして、ここでは、紅茶生産に順序を追い、まず皆さんをあのヒマラヤの広大なカンチェンジュンガの裾野に広がるダージリンの紅茶、茶園まで一気にご案内したいと思いますがいかがでしょうか。 「ダージリン」、 「雷さま」の「生まれる」所の裏を返せば、この場所は上昇気流が多く、「雷」が多く発生しやすい事を示唆します。 上昇気流といえば、その源は、「霧」です。これこそが猛烈な太陽の直射から、ダージリン茶園の茶葉を柔らかく包み、紅茶の生命に高価なアロマの熟成を吹き込んでくれる事はあまりにも有名な事実として知れ渡っています。 息を呑む景観とはこの事でしょうか、海抜、1千メートルから、2千2百メートルの「ダージリン」の丘陵からは、ほんの50マイルの指呼の距離に世界第二高峰のカンチェンジュンガがあり、さらにそのすぐ向こうに世界最高峰のエベレスト(チョモランマ)がそびえます。 良い品質の紅茶生産をしようと、ここの茶畑の広がりは、太陽光線が良く当る南斜面だけを作地として利用し、少しでも条件の悪い西斜面や日陰の北斜面は、せっかくの風土でも遠慮会釈なく放置されています。 このような高地の茶園では、昼間と夜間ではかなりの温度差を生じ、加えて、気温の差により生ずる上昇気流が霧となって、下の茶園から上の茶園に這い登ってきます。 ダージリンには、カルカッタからインド国内航空で、 見渡す限り広大な丘陵に広がる、まるで緑のさざなみのような茶園、そこをヒマラヤの薫風が吹きぬけます。 このヒマラヤのブリーズ(そよ風)こそが、ダージリン茶の美味芳醇の頂点を極める源です。 しかしながら、このダージリンの茶園がいきなりこの土地に出現したわけではありません。 話題は変わりますが、ここで少しインドの茶の歴史をご覧になりませんか。興味のない方は、どうぞ読み飛ばしてください。 |
数千年の歴史を誇る中国茶に比べ、インドにおける紅茶の歴史は意外にも新しく、「茶の種」が最初に中国からインドに着いたのは、今から225年ほど前の1774年にすぎません。 しかしながら、茶の生産がその時期にインドで直ぐ始まったと言うわけでなく、それから19年後の1793年に、ジョセフ・バンクスという英国人が中国の茶生産者を訪れ、茶植の様々な知識を仕入れ、「茶の種と苗」をインドに持ち込みその一部をカルカッタの植物園に植えました。 さらにそれから、26年たった1819年に、当時のアッサム地方の行政官だったデビット・スコットがバンクスの茶樹に関する論文に目をつけカルカッタの植物園に問合せましたが、植物園から取り寄せた苗は大部分枯死してしましました。 その後、ブルース商会と言う会社が登場します。 1834年には東印度会社が「茶委員会」を設立し、その後、茶園はアッサムから北東インド全域へと急速に拡大されていったのです。 もし衛星写真の近撮で空から俯瞰する事ができたら、プラマプトラ河沿いの渓谷は、いまや一本の緑の絨毯を織り成す景観を呈し、観光としても、必見の価値があります。 そして、茶畑の緑の帯びはさらにそこから、ドアー地区、そしてあの「ドルジェ・リン」 つまり「ダージリン茶」のヒマラヤの麓まで160年の歴史を経て広がっていったのです。 茶の樹の生育範囲は、ほぼ海抜8000フィートの高度でも可能であり、トルコからアルゼンチンの北部のジョージアまで生育します。 しかし、「カメリア・シネンシス」〜茶の植物学名〜は、おおむね高温多湿の気候を好み、年間雨量も多く、しかも日照時間の長い事が必要であります。 土壌に関しては、割りと柔軟性に富み、水捌けさえよくしてやれば、砂礫ローム質から粘土質までの広い土壌に生育します。 これらの土壌・風土に適したインドの東北部で作られた多種多様な茶の生産量は、今や世界でも最も多く、2200メートルのダージリンの丘陵からは、世界でも最も香りが高く高価なお茶が、そして、プラマプトラ渓谷沿いのアッサム平野からは芳醇で濃くの深いお茶が年々作出されいることは既にお話したとおりです。 |
| さて、 あのエアー・インディア機の美人客が、カルカッタへの飛行を続けている間に、インドにおける紅茶の歴史など、チョイト小難しいお話を並べ立てしまいました。 その彼女は今どうしているでしょうかね。 そして、背もたれのビデオの映画をスイッチ・オンにして、ちょっとリラックスしていそうな雰囲気ですよ。 それでは、 |
![]()